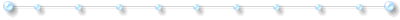| |
好きな相手の星座と血液型、は恋に落ちた女の子の必須アイテムであるらしい。
とかく少女たちは占いやらおまじないやらにこだわりがちで、ラッキーカラーに、ラッキーアイテム。
ラッキーさえつけば、場所でも日付でも時間でさえも、それはそれは素晴らしくて愛しいものに変わる。
雑誌上の小さな文字に、その内容に、彼女たちは一喜一憂できる能力を持っている。
自分にはそれがないのだ、と真砂子はずっと昔から知っていた。
大体からして先ず、小さい頃からろくに学校に通えなかった真砂子に、親しい友人はいない。
そして、彼女自身がその存在を望んでいなかった。
勿論真砂子だって特別独りが好きなわけではない。遊ぶ相手だって欲しかったし、話し相手だって欲しかった。
ただ、いないのなら無理に作ろうとまで思わなかっただけのことだ。
いつの頃だったか、たまたまオフが日曜日と重なっているときに、
テレビ局で知らない大人に「久しぶりに友達と遊べるね」などと言われ、
二度とあの人とは口をきかない、と心に決めたことがある。
そうやって時折、多感で小さな心を無神経な大人が傷つける。
大人になることは、様々なことに鈍感になっていくことだと、真砂子は自分が大人に近づくに連れて、
少しずつ納得するようになっていた。
だからといって、あのテレビ局で感じた痛みを忘れたわけではない。
自分はそうはなりたくない。無神経で鈍感で、頭の悪い大人にだけは。
真砂子が生まれて初めて、その頑なになった心を震わせたは、その数年後のことだった。
それをときめきと言った。
けれど真砂子は知らなかった。
それを恋と言った。
けれど、真砂子は知らなかった。
思いが通じることなど知らなかったから、恋に破れる瞬間も不安さえも、そのときの彼女を揺るがすことはなかった。
ただ、心が震え、身体が震えた。それだけで充分だった。
「今日ね、近いうちにお花見しよってみんなで言ってたんだけど、真砂子都合つく?」
いつも通りに突然かかってきた電話は、底抜けに明るい声でそう言った。
「いつですの?」
「ん〜とねぇ・・明後日」
「そんな急に都合なんて付くわけありませんわ」
「じゃ、ダメ?」
きっと受話器の向こうでは子犬のように丸い目で、縋るような顔をしていることだろう。
容易に想像が付いたそれに、真砂子はふっと笑ってしまった。
「何? 何で笑ってんの?」
「麻衣の顔が面白いから」
「テレビ電話でもないのに?」
「ええ、よく見えますわよ」
真砂子が嘯くと、麻衣が慌てたような声を出した。
「え? 何? ほんとに?」
「馬鹿ね、嘘に決まってますでしょ」
真砂子がころころと笑う。麻衣はおそらくぶすくれているのだろう、もー! などと言いながら、
受話器を指でこつこつ叩いている。どうも、彼女なりの抗議行動らしい。
「そ・れ・で? 真砂子お嬢様は不参加なのでございましょうか?」
「いえ、参りますわ」
「撮影とか大丈夫?」
「ええ、何とか」
正直なところ、ここ最近とくにそちらの仕事が忙しいこともなかった。
オカルトブームが去りつつある今、忙しいのは夏の特番用の撮りが詰まっている時ぐらいで、
真砂子の芸能関係の仕事数は、年々減退しつつある。
現在は霊能者としての仕事の方に力を入れていると言っても良い。
減退期に踏み込もうとしている今の年齢を考えると、こちらの稼業も、あと何年続けられるか解らないが、
ある程度その方面では顔も売れたおかげで、現在は依頼数も多い。今はSPRから調査協力の依頼もある。
芸能活動に支障が出るような(例えば、顔に怪我をするような)調査に協力するな、という意見も無いわけではないが、
それに従う意思は真砂子には無い。
「じゃあ、夕方4時頃に事務所。来れる? もし何だったらぼーさんかリンさんが車回してくれると思うけど」
「大丈夫ですわ、電車で参りますから」
車なんかで家まで迎えに来られたら、家の人間に何を言われるか解らない、と口に出さずに思う。
普段、何かの都合で帰りが遅くなったときも、真砂子だけは家の付近で降ろして貰うことになっている。
極力家から遠ざかった、街灯による灯りでそこそこ明るいと判断できる場所で、送ってくれた車を見送るのだ。
大概の場合、滝川が麻衣と真砂子(時には綾子も)を順番に送っていくのだが、
その場合、真砂子が一番最初に車から降ろされるにもかかわらず、麻衣はそのことを知らない。
彼女は車に揺られているうちに眠ってしまうからだ。眠った子供をわざわざ起こすような悪い趣味はない。
「明後日の4時ですわね」
「うん、じゃあまたね」
さよならを告げて電話を切る。
先ほど敷いたばかりの布団に身体を預けて、真砂子は携帯を枕元に置く。
つい先日、高校を卒業すると同時に購入した携帯電話だ。親には詳しいことは何も言っていない。
ただ「不便だから」と言う理由を示した真砂子に、「弁えて使うように」とごく当たり前の釘だけを差して、親が許可をくれた。
許可をくれた、と言うより、反対するほどの言葉を思いつかなかっただけだろう、と真砂子は知っている。
弁えるとは何だろう。
例えば、18歳にもなって早すぎる門限を守らないことが罪ならば、異性を特別に好きになることも罪だというのか。
他人に迷惑をかけないことと、親に恥をかかせないことが同意で、
「朝帰り」は恥ずかしいこと。「宴会の席へ行く」なんてもってのほかだ。
真砂子は小さく溜息をついた。
息苦しいことが普通だったから、彼女の身体は何年もかけて肺活量を増やす努力をしてきた。
そうやって我慢し続けることが真砂子にとって唯一の防衛手段だった。
我慢という言葉を忘れなければ叱られることはなかったが、愛されることもない。
「可愛げのない子」として扱われることには慣れたし、
不満を口にしてまで他人に自分を理解して欲しいなどとは思わなかった。
(可愛げのない子・・・)
愛くるしい子犬のような顔を思い出す。
それは綺麗な綺麗な、曇りのない青。澄み切った空に似た、疑うことを知らないあの眼差し。
彼女を、あのどこまでも澄み渡った青に例えるならば、自分はあの夕焼けに違いない。
毎日、毒々しく醜い色を放ち、みじめに抗いながらもただ没していくだけの。
小柄な身体でくるりと寝返りを打つと、すぐそばに先ほど放り出した携帯電話が落ちている。
何ともなく手を伸ばして、着信履歴を出してみる。
ぴ、ぴ、という弱気な電子音を静かな部屋に響かせて、20件ほどの着信履歴を眺め、真砂子は小さく笑った。
「・・・麻衣ばっかり」
20件のうち、12件が麻衣からの電話(あるいはメール)だった。
残りは渋谷サイキックリサーチ、綾子、滝川、安原などから数件。
この携帯はテレビの仕事関係者には誰にも言っていない。かけてくるのはプライベートと身内だけだ。
麻衣からのメールは日に何度か届く。
それは他愛もない内容のものばかりで、本当に伝えるべき内容の場合は電話がかかってくるので、
真砂子はメールを一度も返したことがない。
たまには返事返してよ。と、麻衣が拗ねていたが、「麻衣と違って暇じゃありませんから」とつれなく言い返してしまった。
実はメールに関する機能が未だによく解らないのだと、告白するのが癪で放置してある、というのが実状なのだけれど。
最後の1件。つい先刻の麻衣からの電話は、非通知だった。
この頃、麻衣から夜かかってくる電話は非通知であることが増えた。
これがどこから掛けた電話なのかは、追求するべくもない。
麻衣の自宅ではなく携帯でもなく、事務所でなければ、あとは大体の予想が付く。
(わざわざ消去法にするまでもありませんけど)
それでも、一つずつ可能性を考えてしまうだけの未練が、まだ自分の中に残っているのかもしれない。
そんなことを今更、誰に話すつもりもない。自分は諦めたのだと、いつだったか綾子相手に宣言したはずだ。
愛されないから愛さない、なんておかしいと、麻衣は言うだろう。
一方的な愛情を傾け続けることは、純粋な麻衣にとって辛くはあっても難しいことではないのかも知れない。
けれど、と真砂子は思う。
麻衣はこと恋愛に関しては普通の少女だ。破れることさえ叶わなかった初恋を、
少しずつ自分の中で切り替えながら、それさえも愛しながら、
彼女はいつも前を向いて歩いている。その先に何を見つけるかは麻衣次第だ。
けれど、自分には出来ない。
愛されることに渇望し、絶望してきた真砂子が、たった一人見つけた心を揺らす相手。
実物の彼に出会い、行動を共にし、言葉を交わし、そうして気が付いた、彼の中にある孤独。
愛されたいと願うから、誰よりも深く愛してしまう。
それはまるで、病のように執着し、他人や自分の身さえ犠牲にしても構わないと思うほどに求めてしまう。
自分の中にある重く熱い感情を、ナルの中にも見つけたとき、真砂子は恋に破れたことを知った。
真砂子の中で、ナルという存在はこれから先もずっと、特別な場所に存在するだろう。
けれど、それと同じように、おそらくはナルも一生涯、麻衣以外を望まないのだろう。
彼はそれを表に出さなかった。だから、
麻衣が振り向かない限り、彼の想いは真砂子と同じく、報われないだろうと思っていた。
・・・醜い心だと解っていながら、それを願ったりもした。
結局、彼は唯一無二の存在を手に入れ、真砂子は逆にそのチャンスさえ失ったけれど。
ナルと真砂子は、同じ感情を抱えている。
向いている方向が違うだけで、同じだけの重さと暗さを抱えている。
ナルは、相手がこちらを向いて抱きしめてくれた。
真砂子は、相手を振り向かせることが出来なかった。
違いはただ、それだけ。
「・・・麻衣のように、走れたら」
あの子犬のように走れたら、真っ直ぐにひたすらに走ることが出来たなら、何か変わっていただろうか。
例えば、あるがままの自分で。走ることが出来なくとも、せめて今、たった一歩でも踏み出せたなら。
(少しは変わるかしら)
空に馴染めないままの自分でも。
何か、彼の中の何かを動かすことは出来るだろうか。
「あたくし、あなたが好きなんです」
真砂子の言葉に、ナルは何の反応も見せなかった。
「何かお返事いただけませんこと?」
「原さんの能力は評価していますが、ご自身の感情に興味はありません」
「なら、この能力と引き替えに要求しても宜しいかしら?」
「・・・何を?」
「くちづけを」
誰かが真砂子の背後で息をのんだ。
「ま・・・真砂子? 酔ってる?」
「真砂子ちゃん・・・酔うと大胆になるクチか」
「何を呑気なこといってんのよ、くそぼーず」
「ま、まぁまぁ落ち着いて・・・」
桜の花びらが舞い散る中、安原と滝川が見つけだしてきた穴場お花見場は、
確かに他の宴会はまばらで、それなりに静かに華とアルコールを楽しめる場所だった。
このお花見の席に大量の日本酒を持ってきたのは滝川で、
目まぐるしいほどの早さで栓を開けられていく一升瓶は、主に真砂子の傍らに置かれていた。
真砂子は、泊まりでない飲み会の席ではアルコールを一切口にしない質なので、
今日のような(日帰り予定の)飲み会に真砂子が参加する際には、必ずウーロン茶などのソフトドリンクが購入される。
麻衣が最近少しずつだが、ビール程度のアルコールを口にするようになったので、
アルコール初心者の彼女が酔って一升瓶を薙ぎ倒すことのないように、
素面の人間のそばに設置するのが、暗黙の了解になっていたのだ。
飲み会で素面と言ったら、真砂子かナルだけだ。ナルが一升瓶の番など、当然するわけもない。
諸々の事情を踏まえて、唯一の安全地帯とも言える真砂子の隣に鎮座していた一升瓶。
それなのに。
彼女の手には紙コップ。底の方には無色透明の液体。
真砂子が日本酒を飲んでナルに絡んでいったのだろうことは、現場の状況から容易に想像が付いた。
が、勿論それは、全く予測していた事態ではなかった。
「五月蝿いですわ。外野は黙ってらして」
「真砂子ぉ〜〜」
麻衣が情けない声を漏らす。この席で一滴もアルコールが入っていないのは、現在のところナル一人だけだった。
その『素面の』ナルに向き直って、真砂子は居住まいを正した。
「一度だけで構いませんわ」
「お断りします」
「何故?」
「そうしたいと思わないから、と言えばお解りになりますか?」
「解りませんわ」
ナルが溜息をついた。読んでいた本を片手に立ち上がって、真砂子を侮蔑の表情で見下ろす。
「付き合いきれない」
「あら、麻衣には付き合えても、あたくしにはお付き合いいただけませんのね」
騒がしかった周囲が一瞬にして静かになる。が、ナルは眉一つ動かさなかった。
「どういう意味でしょう?」
「真夜中に麻衣を部屋に置くことは許せても、あたくしの話を聞くだけの時間の無駄は許せない、と言うことでしょう?」
真砂子がにっこりと笑ってみせる。ナルが痛いところに触れられたような苦々しい顔をして、瞬時に麻衣を睨んだ。
ナルと麻衣がそういう関係にあることは、周囲の誰にも知らされていない。勿論、真砂子も直接麻衣に聞いたわけではない。
3割の予想、5割の確信。残りははったりみたいなものだった。
が、ナルからしてみたら、麻衣が真砂子に口を滑らしたのだと思っただろう。
「ち、違う! あたしじゃないからね!」
両手を振って弁解する麻衣の姿は、逆に真砂子の言葉を裏付ける結果となってしまった。
「ちょっと待て! 麻衣、お前いつの間にそう言うことになったんだよ!」
「や、あの・・ちが・」
「ほーらみなさい、この間の賭はあたしの一人勝ちねv」
「越後屋、一生の不覚です。今回は女性の第六感に完敗ですねぇ」
「ほらほら、ぼーずは3万よ! さっさと払いなさい」
「リンさんも負けですね。いくら賭けてましたっけ?」
「滝川さんと同額だったかと」
「じゃあ3万ですね。僕からの支払いも含めると、総計で・・・」
「・・・皆サンで賭けてはったんですか・・・・・・?」
「綾子・・・暫く遊んで暮らせるね・・・・」
「あら、一晩飲み歩いたら消えちゃうわよ、この程度なら」
「じゃあ今夜の二次会は、松崎さんの奢りって事でv いやー、嬉しいなぁ」
「ふざけないでよ、何であたしが・・・」
「今夜は飲むぞ〜〜〜〜!!!!!!」
アルコールも手伝って、一気に騒々しさが倍増した周囲に、ナルはもう一度眉を顰めた。
早々と立ち去ろうとして、「車もないくせにどうやって帰る気?」などと綾子に突っ込まれ、
彼は喧噪からやや離れた場所に腰を下ろした。再度読書を試みる腹づもりらしい。
真砂子は酒が引いてきた重い頭を抱えて、ナルの方へ歩み寄った。
「ナル」
彼は迷惑そうな顔を隠そうともしない。
「アルコールが冷めるまで近寄らないで頂きたいんですが」
「もう冷めました」
冷静な真砂子の声にナルはちらりと彼女の顔を見上げ、興味なさそうに本の方へ目を伏せた。
「お隣宜しいかしら」
「出来ればご遠慮願いたいですね」
否定的ではあるが全くの拒絶ではなかったので、真砂子はナルの隣に腰を降ろした。
「・・・ごめんなさい」
「悪いと思うのなら、初めからしなければいいものを」
「解ってますわ。でも、どうしてもそうしたかったの」
離れたところで見ると、麻衣や滝川たちの饗宴は殊更楽しげに見える。
「麻衣が、羨ましかったんです」
青空になりたかった。子犬になりたかった。…麻衣のように、なりたかった。
「原さんの方が有能ですよ」
本を見たまま答えるナルの言葉に、真砂子が少しだけ驚く。
きっと深く意識していったのではない、それは彼なりの正当な評価なのだろう。
真砂子が悲しげに笑う。
「有能であることよりも、あなたに選ばれたかった」
その笑顔を、ナルは見ていない。彼の世界に、真砂子は踏み入ることさえ出来ない。
「ナルが好きでしたわ」
「有り難うございます、と言うべきですか?」
単調な言葉でも、返ってくるのが嬉しい。
「らしくないですわね」
「今日の原さんも」
真砂子は目を見開いた。まさかそんな風に返されるとは思ってもみなかった。
「・・・いつもの、あたくし?」
「ええ」
一定の速度で捲られるページ。一度も揺れることなく書物に向けられる視線。淡々とした口調。
真砂子はもう一度笑った。今度は悲しくはなかった。けれど、一筋だけ涙が零れた。
「きっと、お酒のせいですわ」
赤のままで良いと、自分のままでいて良いのだと。
(・・・きっとお酒のせい)
ナルがいつもより優しく見えるのは、きっと。
「まっさこー! 帰りに綾子がアイスクリーム山ほど奢ってくれるってぇ〜v」
麻衣が大きく手を振ってこちらを見ている。
自分の恋人にたったいま告白したばかりの女性が、彼と二人っきりで座っているというのに。
(危機感が足りませんわよ、麻衣)
愛しい友人に、小さなイジワルを。愛しい二人に、小さな波風を。
(少しは焦りなさい)
「ナル、行きません?」
読書中のナルの手をわざと引っ張る。体勢を崩すことなくこちらを睨んだナルに柔らかく微笑みかけた。
「結構です」
「そう・・・」
引っ張った手の甲に小さくくちづけて、真砂子は麻衣の方へ歩き出した。
ナルの表情は、敢えて見ないことにした。
「・・・・・・真砂子・・・」
「どうしましたの? 麻衣」
口を開けたままこちらを見る麻衣に、真砂子はわざと笑ってみせる。
たったいま繰り広げられた光景に、あれだけ騒いでいたメンバーは唖然としている。
もしかしたら、真砂子の背後にいるナルがブリザードを吹き荒らしているのかも知れない。
「・・・・・・・・・やったね?」
「ええ、いけませんでした?」
「あたしでも人前ではしたことないのに」
「そんなこと、こちらの知ったことではございませんもの。そんなに心配なら首に縄でも掛けておいたらいかが?」
「宣戦布告?」
「いえ、」と言葉を切って、真砂子は麻衣を見た。自然に笑みがこぼれる。
「戦線離脱宣言ですわ」
「そか」
麻衣が少しだけ悲しげな、そして少しだけ申し訳なさそうな曖昧な表情を浮かべた。
彼女はすぐに真砂子の後ろ、麻衣自身が手に入れた黒衣の男へ視線を移す。挑むような目で。
「・・・じゃあ、あたし宣戦布告してこよっかなぁ」
立ち上がった麻衣を止めようとした滝川の手を、綾子が引っ張って止めた。
歩き出した麻衣に、すれ違いざま、真砂子が小さく呟く。
「誰に?」
解りきった質問に返ってきたのは、予想通りの答えだった。
「ナルに」
アルコールのせいか、頬を赤らめつつもにっと笑った麻衣の顔は、もう少女ではなかった。
真砂子の嫌がらせを受け、大人しくその場にじっとしているような人ではない。
ナルはとっくに別の桜の木の影へ移動していた。
その彼の行く先を見失ってしまったのか、ほろ酔い加減の千鳥足で麻衣がナルを呼んでいる。
遠目に見ればすぐに見つかりそうな程近くにナルと麻衣は立っているのに、麻衣にはどうしても見つけられないらしい。
「賭けない?」
その光景を眺めていた綾子が、突然にやりと笑った。
「またですの?」
溜息混じりに真砂子が言うが、大人たちは聞く耳持たなかった。
「どっちが先に折れるか」
綾子が人差し指を空に向かって立てている。
逆の手の紙コップには彼女が特に好んでいる銘柄の日本酒が入っている。
「麻衣が先に諦める方に、今夜の寝床提供を賭ける」
滝川が持っていたつまみのさきいかをくるくると回した。
「渋谷さんが耐えられなくなって車に戻る、に一票」
安原の言葉に、リンが無言で賛同した。
が、綾子は不敵な笑みを浮かべて周囲を見渡す。
「まだまだ甘いわね。麻衣がナルを発見する、に、二次会の飲み会の飲み代」
「そうか、動物だったなアイツは」
「でも、三半規管も怪しい感じですよ、今の谷山さん。帰巣本能も働かなくなってそうだし」
言いたい放題のメンバーたちに、真砂子はおっとり笑った。
「ナルが仕方なく麻衣を拾いにいく、に賭けますわ」
「へぇ、新展開じゃない」
楽しげに笑った綾子の視線の先で、麻衣が地面にへたりこんだ。予想以上に酒の回りが早かったらしい。
「あらあら、もう潰れちゃったわよ、あの子」
「誰か助けにいかねーと」
「賭は破棄ですかね」
よっこらしょ、と年寄りくさいかけ声と共に立ち上がった滝川に、その腕を引っ張って真砂子が絶世の笑顔を見せた。
「あたくしの勝ち、ですわ」
「へ?」
桜の木の下、座り込んだ麻衣の腕を引っ張り上げる青年は、諦めと呆れのなかにほんの少しだけ愛情を滲ませている。
少女を引き起こし、両腕で抱えたまま車の方へと消えていった青年の後ろ姿に、真砂子は小さく別れを告げた。
幼いまでの恋に、それでも愛したあなたに。切ない思いと、切ない時間に。
『あたくし、ナルが好きでしたわ』 |
|
|
 --+--- 赤 と 青 ---+--
--+--- 赤 と 青 ---+--