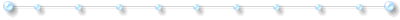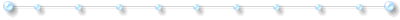| |
だって、気になるんだよ。
理由なんて解んない。
なるは冷たい。
すごく取っつきにくいし、愛想はないし。
でも、あたしは何故か、ここから出ていきたくなかった。
なるの、家から。
みんなが順番に帰っていくのを、なるは硝子玉の瞳で見ている。
ジョンは、ゆっくり休んで下さい。いろいろあって疲れてますやろ。
と言い残していった。
まさことあやこは、最後までなるに抗議していたようだった。
ぼーさんは全く身動きしなくなり、りんさんがぼーさんの背を押して
引きずるように部屋を出ていった。
すれ違いざま、料理はできそうですか?と聞かれ、
つい、はい。と答えてしまった。
りんさんはふっと微かに笑んで、それじゃあ、何か困ったら
私の家は隣ですから、呼んで下さい。と言った。
広いリビングから、一人消え、二人消え。
気付いたら、いつの間にかそこにはあたしとなるしかいなかった。
何となく、なるはあんまり喋る人じゃないんだろうな。と思う。
だから、彼と二人になれば訪れて当然の、沈黙。
訊いても良いのかな。
気になることがたくさんある。
あたしは、ちょっと離れたところで書類を整理しているなるに目を向けた。
英文だらけの書類。
「ねぇ、…なる?」
あたしの声に反応して、なるが振り返る。
先を促すようななるの目に、あたしは物怖じしてしまう。
あんまり聞かれたくないことかもしれないし、また機嫌が悪くなったら、
どうしたら良いか解らない。
「何だ?」
「…訊きたいこと、あるんだけど」
なるって、日本人じゃないの?
結構勇気がいる質問だった。
どうしてこんなに勇気がいるのか、それさえも解らないのに。
「本籍はイギリス」
「イギリス?帰国子女ってこと?」
いや、と言ってなるは言葉を切った。
「母親が日本人だったからな」
ハーフってことかー。
意外とあっさり答えが得られて、あたしは嬉しくなった。
訊けばちゃんと答えてくれるんだ。
「だから、本も書類も全部英語だったんだね」
既に、なるは片づけ作業に戻っている。
それでもあたしは、なるに質問を続ける。
「なる、ここに一人で住んでるんでしょ?留学中?」
なるは首を振った。ノーってことかな。
「なるは幾つ?」
これにはちゃんと言葉で答える。
「今年で20。ちなみに、お前は今年で19」
次に訊こうとしていたことだったので、
あたしは急いで新しい質問を考える。
一番疑問に思っていることは、口にするのが躊躇われた。
どうして、あたしはナルの家にいたの?
「あたしとなるって、上司と部下?」
「そう」
なるはあたしを見ない。顔色も変えない。
「…あたし、よくここに来てた?」
「週に1,2回程度」
それが、頻繁と呼べるのかそうでないのか、判別が付かない。
「泊まったりも、してた?」
精一杯間接的に訊いているつもりだったのに、なるは核心をつく。
「夕べ何があったかが、訊きたいのか?」
あたしは顔が熱くなるのが解った。
「…うん」
だって、気になるよ。
上司と部下。それ以上じゃないなら、
あたしがなるに片思いしてたのかもしれない。
逆は、ちょっと考えられないな。
何たってなるは絶世の美形だ。
あたしは、これと言った特徴もないそこらにいる普通の女の子だった。
(鏡は素直だからなぁ)
深い闇色の瞳が、ふと緩んだ。
「僕は昨日、ここで寝たんだ。…誰かさんが
人のベッドを占領してくれたおかげでな」
誰かさんって、あたし、だよね、どう考えても。
なるは苦笑うようにあたしを見た。
「霊が見えたのが不安だから、一人で寝るのがイヤだとだだをこねて、
勝手に寝室を陣取ったんだ」
中から鍵が掛かってただろう?と言われて、思い出す。
そういえば、あたし鍵を開けた覚えがある。
「…安心したか?」
からかうようななるの顔を、むーっと膨れて睨み付けると、
「朝から何も食べてないのに、元気だな」
そうだ。あたし、何も食べてないや。
いろいろありすぎて、すっかり忘れてた。
「なるは、おなか空かないの?」
さらっと返される。
「別に」
…そうやって返されると、なんか食べたいって言いにくくなるじゃんか。
でも、空いたって自覚すると、急激におなかが鳴り始める。
「なんか作って食べても良い?」
どうぞ、とキッチンの方を手で示される。
なるは食べないの?と訊くと、
「食べる」
と一言。
アンタ、自分で作りたくないだけか…?
冷蔵庫には、男の一人暮らしとは思えないほど
きっちりと中身が収まっていた。綺麗に整理されて。
あたしは料理を忘れてなかった。
何とか形になったスープスパゲティーをリビングに運ぶと、
なるはノートパソコンと向き合っていた。
さっきまで書類やら雑誌やらで埋もれていた机の上は
すっかり片づけられていて、二人が食事をするだけのスペースができている。
「できたよ、なる」
「ああ」
「なる、好き嫌いは?」
別に、と答えてパソコンの電源を落とす。
会話の殆どを単語で済ませるなるに、不満を感じないわけではないけど、
それよりも先ず、空腹を満たしたかった。
「ここには、みんなよく来るの?」
「殆ど来ない。リンがたまに来るぐらいだな」
ふーん。やっぱあたしは、仲間内でも特殊な例だったのか。
「なるは、淋しくない?」
なるは怪訝そうに聞き返す。
「…淋しい?」
「こんな広いところに、普段ずっと一人なんでしょ?休日とか」
訊ねられたことに間を置かずに答えながら、なるは書類を見ている。
あたしは、なるが座っているソファの横の床に直接座った。
「大概は事務所にいるから、あまり一人でいる実感はないな。
どちらかというと、一人の方が気が楽なんだが」
「…あたしがいると、迷惑?」
一人の方がいいなら、あたしはなるの迷惑になっているのだろうか。
なるは、予想もしていなかったことを訊かれたのか、
驚いた顔をしている。書類を捲る手が止まった。
「あたし、いない方が良い?」
なるは黙っている。どこか困ったような。
「なる?」
彼にしては珍しく、はっきりしない態度。
…図星をつかれて、答えを探してるの?
「あやこのとこに泊めて貰おうか?」
なるは黙ったままだ。
あたしは立ち上がった。さっき、綾子が帰っていくときに
電話番号を書いていってくれた。
何かあったら、何時でも良いから電話しなさい、と言って。
そういえばあたし、なるの迷惑とか、事情を考えずにいた。
なるは人といることを嫌うって、まさこが言ってたのに。
拒絶を示すなるが悪いんじゃない。…でも、痛む心はどうしようもない。
(あたし、やっぱりなるを好きだったのかな)
だから、こんなに胸が痛いの?
部屋の端に置かれた電話に手をのばすと、
後ろから腕を捕まれた。
「…なる」
「何をする気だ?」
「何って、電話…。あやこがいつでも電話して良いって言ってたから」
あやこなら泊めてくれるかなって。
それ以上は言葉にならなかった。
(なるって意外と力強いなぁ)
すごく細いのに。
こんな状況で考えるべきことじゃない。
解ってるけど、頭が働かない。
あたしの身体は、なるの腕の中に閉じこめられていた。
唇を塞がれて、白い壁に押しつけられる。
抵抗。…抵抗しなきゃ。
やっとそこに気が付いたときには、なるの唇は離れていた。
すぐそばにある、恐いくらい綺麗な顔。
「行くな」
静かに紡がれた言葉を、理解するだけの余裕があたしにはない。
ただ、漆黒の目を見ているだけだ。
全てがどこか遠いところで行われていることのようで、
現実味がない。
何も言えなくなったあたしの唇をもう一度塞いで、
唇が離れる直前、あたしはなるをひっぱたいていた。
なるの頬に、くっきりと赤い痕。
真っ赤なあたしに対して、なるの表情には変化がない。
「なっ…なにす…」
言葉が上手くでてこない。
あたしの手首は壁に押しつけられたまま。
身体はなるの腕に拘束されている。
この状況は何なんだろう。
どうしてあたし、なるに抱きしめられてるの?
知らない人なんだよ。ついさっきまで、警戒してたはずなのに。
(ソンナハズナイ。マイハカレヲ知ッテル)
頭のどこかで響く声。でも、あたしはパニックを起こしていて、
そんなこと気にしていられない。
「麻衣…」
耳元で囁かれるなるの声。低い、心地よい声。
抱きしめられたときに気付いた。
あの匂い。あのベッドの匂いは、やっぱりなるのものだ。
包まれるような安心感。混乱する思考のどこかで、
あたしは安堵してる。やっと、居場所を見つけたような。
でも、なるはあたしといるのイヤでしょ?
考えてるだけのつもりだったのに、いつの間にか声に出していたらしい。
「そんなこと一言も言ってない」
なるが急に返事を返したから、あたしは現実に引き戻された。
そう、現実。
「やっ…!は、離して!」
必死にもがくけど、なるはびくともしない。
頭がくらくらする。何がどうしてこうなったの?
「お願…い、離して…。やだ、…恐い」
涙が浮かぶ。泣かなくちゃいけない理由なんかないのに。
あたしが泣きだしたことに気付いて、なるが腕の力を緩める。
解放されたわけじゃないけど、さっきよりはましだ。
なるは口を開かない。あたしも何も言えない。
時間だけが、過ぎる。
どれぐらい経ったのか、押さえられた手首がじんと痛んできた。
心臓より高い位置に固定されているからかもしれない。
話すきっかけを失うと言葉も出なくて、あたし達は黙ったままだ。
でも、いつまでもこうしていても仕方ない。
なるの肩越しに見える窓から、夕日が微かに射し込んでいる。
「…なる、手痛い…」
長い間黙ってたから、声が掠れている。
なるはあたしの手を解放した。でも、その代わりに
今度はあたしの腰の腕を回す。
前より深くなった抱擁に、あたしはもう抵抗さえしない。
ただ、なるの背に手を回して抱き返すのは、躊躇われた。
「あたし、ここにいて良いの?」
「ああ」
「迷惑じゃない?」
「さっきから、そう言っている」
言葉の割に、声は暖かい。
…早く、記憶を取り戻したい。
朝起きてから、初めて切実にそう思った。
なるの家は謎だらけだ。
何たって、あたしの着替えが一式揃っている。
あたしは服の袖に付いている血が気になって、なるに訊ねてみた。
なるはクローゼットを漁りながら、何でもないことのように答える。
「僕の血だ。気にするな」
「僕のって…、どっか怪我してるの?!」
「腕。調査の時に切った」
うそ!あたし、さっき思いきり腕触っちゃったじゃない。
あたしはなるの腕を取った。
「何で早く言わないの!…まだ痛い?」
「もう痛みはない」
大丈夫だ、とあたしを押しやる。
そういえばあたし、顔も殴っちゃったよなぁ。
そっとなるの顔を見ると、そこには何の痕も残っていない。
「ほんとに?」
「それより、そろそろ湯を止めなくて良いのか?」
はた、と動きが止まる。
「そうだった!まずい、溢れちゃう!!」
ばたばたと走り去るあたしに、なるの呆れたような眼差しが向けられた。
「で、何か思いだしたか?」
入浴後、冷蔵庫に入っていたプリンをほうばっていたあたしに、
なるは問いかける。
「特に、今のところ何も」
スプーンを口に運んだまま答えると、
なるが不意にあたしの口元を長い指で拭う。
「あ、でも、なるのことはちょっと解ったよ」
「僕のこと?」
「うん。いっぱい教えてくれたから」
なるは、あたしの口に付いていたプリンを拭っていたようだ。
白い綺麗な指を見せて、苦笑する。
「子供か、お前は」
「む〜。うるさいやい」
どうする?と目で問われて、あたしは目の前にあった指を舐めた。
何となくそんな行動をとった自分に驚く。
…あたし、今。
一気に顔が熱くなる。
「…子供、と言うより、動物だな」
なるは呆れ顔。
あたしは、それ以上追求されるのが恥ずかしくて、
何か別の話題に変えようと、必死で頭を回転させる。
「…あたし、思い出せるのかな」
ぽつり、と口からこぼれ落ちた言葉。
記憶って、戻るものなの?
「別に、思い出さなかったからと言って、生きていけないわけじゃない」
そりゃそうなんだけど。
「でも、ぼーさんとかあやこのことも、ちゃんと思い出したいよ」
みんなが示してくれる愛情が、理解できないのが辛い。
「なるのことも、全部思い出したい」
どんなにいろんなことを訊いても、
過ごしてきた時が取り戻せる訳じゃない。
どこかに空洞があるみたいな感じがする。
「いいかげんなことを言いたくはないが、多分大丈夫だろう」
「どうして?」
「お前は、今日初めてあったばかりのぼーさんや松崎さんを、
抵抗なくニックネームで呼べてる」
そういえば、そうだ。
何だか、さんづけしたりするほうが、違和感があって。
記憶もないのに、違和感なんておかしいと自分でも思うけど。
「大丈夫、かな?」
「多分な」
寝て起きたら、元通りになってれば良いのに。
呟きはなるの耳に届いたらしい。
微かに笑ったなるの顔が、あたしの、消えてしまったはずの
記憶のどこかを揺り動かした。
会いたい、と、思った。
…誰に?
「本気…?」
後込みするあたしに、なるは相変わらずの無表情。
「冗談を言ってどうするんだ?」
「どうするって、…言われても」
食事が済んだ。お風呂も入った。テレビも、面白くない。夜も更けてきた。
どうしようか?と尋ねるあたしに、なるは平然としている。
「寝ればいい」
「…どこで?」
この家には、なるしか住んでない。だから、ベッドは一つしかない。
また、なるがリビングで寝るのかな、と思ったけど、
彼はあっさりこう答えた。
「僕は二度とご免だ。まともに眠れない」
じゃあ、どうするのよ?
「ベッドは一つだ。床で寝たいと言うのなら止めないが?」
あたしは沈黙する。…どうしよう。
なるは溜息を一つ付いて、そのまま寝室へ入っていく。
あんたには羞恥心とか、そういう恥じらいってもんがないのか。
だって、いくらちょっと普通より大きいサイズだっていったって、
あのベッドは一人用だ。二人で寝るには小さすぎる。
困り切っているあたしを、寝室から声が呼ぶ。
「どうするんだ?」
…解ったよ。もういちいち考えんの止めよう。
あんまりぐずぐずしてると、ほんとに床で寝かせられそうだ。
あたしは、寝室へ足を踏み入れた。
心臓が痛いくらいに高鳴っている。
なるは適当にベッドを整えると、かちかちになっているあたしを見て、
眉を顰める。
「…何を考えてるか、見るだけで解るな」
「…っうるさい!なるがおかしいんだよ」
「何で僕なんだ?」
「普通は動揺するもんでしょ?!」
「お前がそうだからといって、他人も同じだと思うな」
違う。なんか違うだろ、それは。
腹立ち紛れに、あたしはベッドに飛び込んだ。
ベッドのバネが、大袈裟な音を立てた。
こうなったら、なるより先に寝て、ベッドを占領してやる。
「ベッドが壊れる」
なるは全然動じてない。まるで子供扱いだ。
俯せになったあたしの頭を軽くたたくと、部屋から出ていった。
ふーんだ!
何だか悔しい。なるに勝てない。
「…結局、どんなかんけーだったんだろ」
上司と部下、だとなるは言った。
でも、何かしっくりこない。
上司と部下?…ただの仕事仲間を、抱きしめたりするだろうか。
それとも、なるは元々そういう人なのかな。
また、まさこの声が響く。
「なるはぁ、他人が一緒にいるのはイヤなんだって」
小声で呟いてみる。他人と一緒にいるのがイヤな人が、
他人であるあたしを、引き留めたりするだろうか。
考えれば考えるほど解らなくなる。
すごく簡単な答が一つある。
この言葉を当てはめてしまえば、全てがすっきりする。
でも、それはあり得ないと、思うんだけどなぁ。
色々頭を巡らしていると、だんだん眠くなってきた。
「まだ起きてるのか」
なるの声が降ってきたけど、まともな反応が返せない。
「んー。…もぅ寝るよぉ」
眠たい。自分で思ってたより、ずっと疲れてるみたいだ。
意識がなくなる直前、なるに抱き上げられたような気がしたけど、
多分気のせいだろう。
夢に出てきたのは、なるだった。
なるは見たこともないほど柔らかく微笑んでいた。
なる…、ナルじゃ、ない。
あたしは彼の名を呼んだ。
久しぶりだね、と笑った彼の顔は、あたしが大好きだった、あの笑顔…。 |
|
|